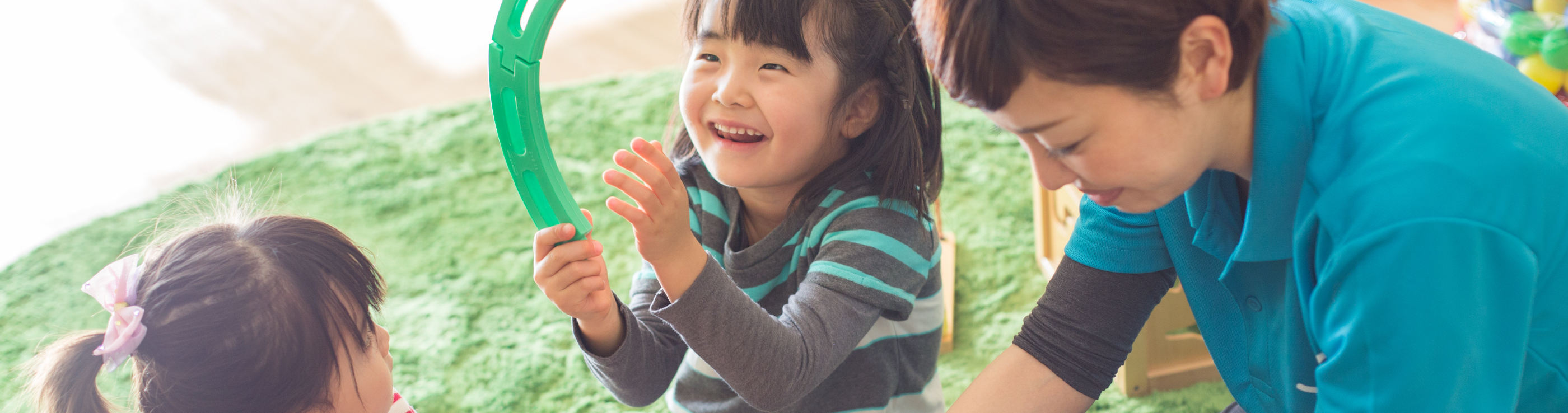

2025.05.15 お知らせ
キッズホームFIT越谷教室の川鍋です。
平素は当教室運営にご理解ご協力をいただきありがとうございます。
当教室のメールアドレス変更のご連絡をさせていただきます。
5月14日(水)の朝方より、当教室のメールアドレスに対して不正ログインのセキュリティが検知され、利用停止の措置がなされました。
その為、大変恐縮ではございますが当教室のアドレスを本メールのアドレス(kidshomefit1@yahoo.co.jp)へ変更をさせていただきます。
保護者様、関係者様にはご不便をおかけしお詫び申し上げます。尚、セキュリティにより不正ログインは防止されていますことお伝えさせていただきます。
※5月13日(火)18時より以前のアドレス(kidshomefit@yahoo.co.jp)へいただいたメールの確認ができておりません。
該当時刻以降、メールを送られた方は大変お手数ですが新メールアドレスに再送信をお願い致します。
ご質問等ございましたら遠慮なくご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。
キッズホームFIT越谷教室 川鍋
2025.05.07 FIT越谷FIT通信
皆様こんにちは☀
もう5月ですね🎏✨

















2025.05.02 FIT越谷FIT通信
 上記の写真を見たとき、一番はじめに目に止まった所ははどこでしょうか?
上記の写真を見たとき、一番はじめに目に止まった所ははどこでしょうか?
誰しもが、欠けた円の方の欠けた部分に目がいったことかと思います。
これは、できている部分よりもできてない部分に注目しやすいという人間の心理が働いている為のようで、ごく自然なことなのです。
人の欠点ばかり目についたり、子どもの不足している部分に悩んでしまったりということは当然のことなんですね。
ですが、負の部分にばかり目がいくとそのことしか考えられなくなり、悪循環な思考に陥って自分自身も辛くなってしまいますよね。


負の気持ちを消したり否定することなく、そのままを捉えてあげると、物事を多角的に考えやすくなります。
また、一歩引いた視点に立てるようになると、負の部分だけでなく次第に良い部分も見えてきます。
 川鍋
川鍋